観光ブームのその中で
インバウンドツーリズムが盛り上がってます。
東京・大阪・京都の大都市だけでなく、地方都市でも外需を取り込もうと必死です。
XX年前に作った街案内情報を掘り起こし、外国語訳をつけ、おらが町も”この地にしかない魅力”を発信して観光で地方創生!と鼻息荒いですが、なんでしょう この違和感。
国のツーリズム政策のご意見番デービッドアトキンソン氏も情報発信の前に中身の整備からでしょ!とおっしゃっております;

今からでもできるインバウンドブームへの対策としては記事に書いてある通りだと思います。
外国人にその地をより深く理解してもらうため、観光資源/コンテンツの整備、外国人が滞在しやすいまちづくりを、というのはごもっとも。
でも、観光を盛り上げよう、観光で盛り上げようとなればなるほど長期的に矛盾を抱えた街になってしまうのではないか、と考える今日この頃。
手段としての観光
例えばNHK大河の舞台となる町の場合。
大河に取り上げられる!これは千載一遇の棚ぼたチャンスやで!観光で街を盛り上げなっ!
となります。
分かります。だって、ゆかりある人物が大河で取り上げられるなんて滅多にないし、間違いなくどこかの旅行会社がパッケージツアー組みますから。
でもその大河が終わった後に残るものはなんでしょう。
大河の影響力がある1年そこそこのためにかけるお金。投資対効果は十分に出せるのでしょうか?多分出せるのだろうけど、その投資の結果残るものは、長期にわたって活かせる資源に成長できてるのか疑問が残ります。(単年でも黒字になれば良いという意見も全然ありですが。)
観光で盛り上げよう!ってなると、どうしてもイベントちっくになり、持続性がなくその地に根付いていかないのかなーと。
目的としての観光
アトキンソン氏は書いておられます;
”まずは地域の可能性を探り、どういった観光資源をいかに整備し、どういう観光地開発をするかを決めるのが先決です。”
さっきの記事
これって、観光が目的になってます。その結果が;
誰も見ていないホームページの開設や観光動画の掲載、誰もフォローしていないFacebookでの情報発信、ゆるキャラやキャッチコピーを使ったブランディング、交通機関頼みのデスティネーションキャンペーンなど、昭和時代のマインドのまま展開されている情報発信の事例は枚挙にいとまがありません。
さっきの記事
観光産業は成長している!僕も私も乗り遅れてはならん!ということで頑張った結果だと思うんです。でも待てよ、と。観光とはその地にある光を観ることではないのか、と。観光が目的化した結果、謎のゆるキャラができあがり、ゆるキャラグランプリでの勇姿を地元のニュース番組で取り上げられ、わっはっはってなります。
で、その街はどうなるのか。
観光が目的って言えば、飛騨高山もこれに該当するのかなと。
観光産業で食ってきたし、これからも食っていきます、先人たちが築いてきた文化・町並みが僕らの観光資源ですってなると、過去の遺産で食いつなぐだけであって、後世に残すものを新たに創り上げてないことになりませんか?過去からの遺産は未来永劫その価値を維持できるのかって問題になります。(維持されれば問題ない?っていうのもちょっと違うと思うし、実際維持できてないし)
結果としての観光
これからの観光ってあくまで「結果」だと思うんです。
それぞれの街が長期的なビジョンを持って、自分たちの街がどうやって生き残っていくかを考え抜いた結果が共感を呼び、その地を訪れるって人が増えていくと思うんです。
だから刺さらない人には刺さらないけど、ハマる人にはがっつりハマる。なんてったって、彼/彼女の人生を豊かにする資源を求めてその街を訪れるのですから。
高齢化・人口減少、大都市東京との格差等々の問題山積の中で、地方都市としてこれからの時代をどう生き残るのか・どんなまちをつくっていくのか、まずはこの問いに対する答えを考え抜かなければいけないのかなと。
その街の生き様に共感して訪れる人がいれば、その「人」と「まち」のインゲージメントは強いものとなり、結果、観光客と関係人口が増加し、生き残りをかけた地場の産業も支えられるんじゃないかなーと。
せっかくのインバウンド特需を受けられている今だからこそ、バブルに浮き足立つことなく、自分たちの街をどうしたいかを考える機会と捉えるべきではないかな〜と考えてます。
ま、知らんけど。
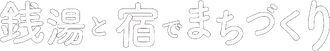



コメント